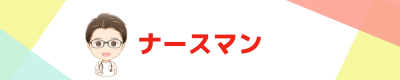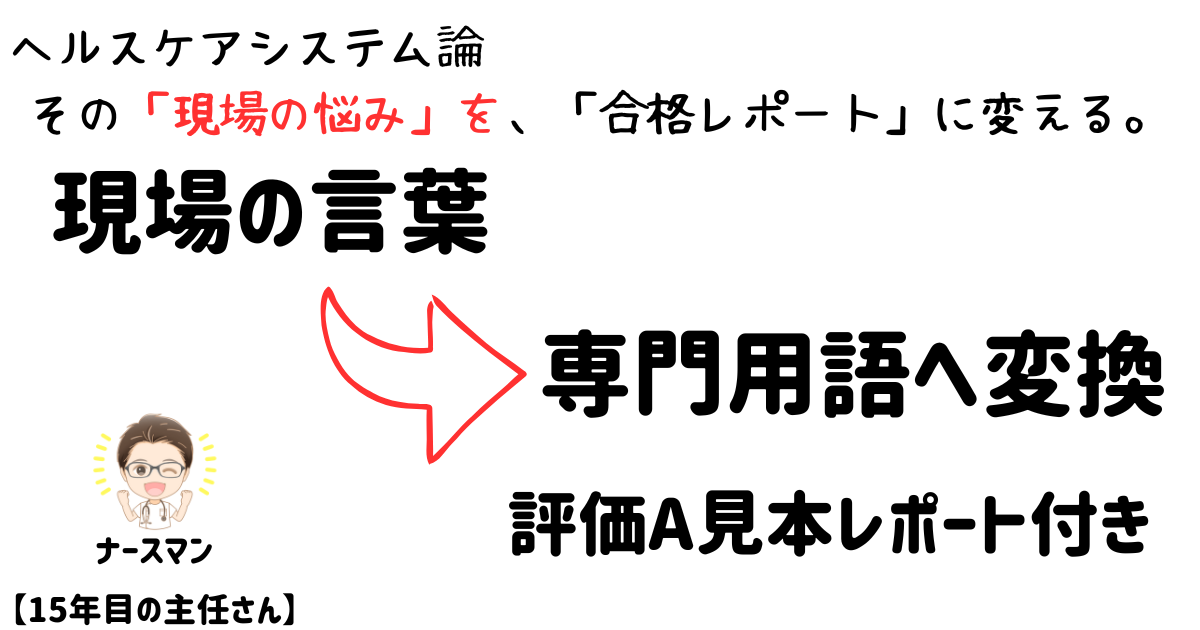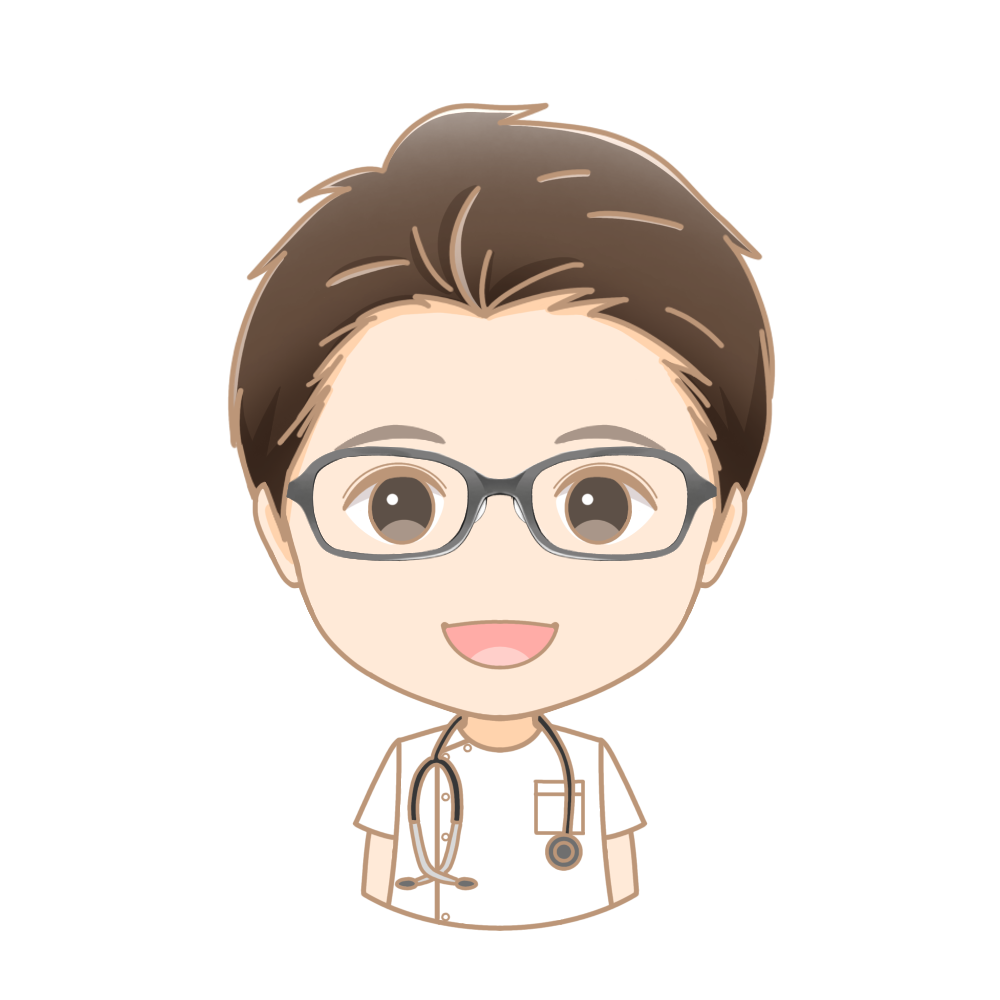※当ページのリンクには広告が含まれています。
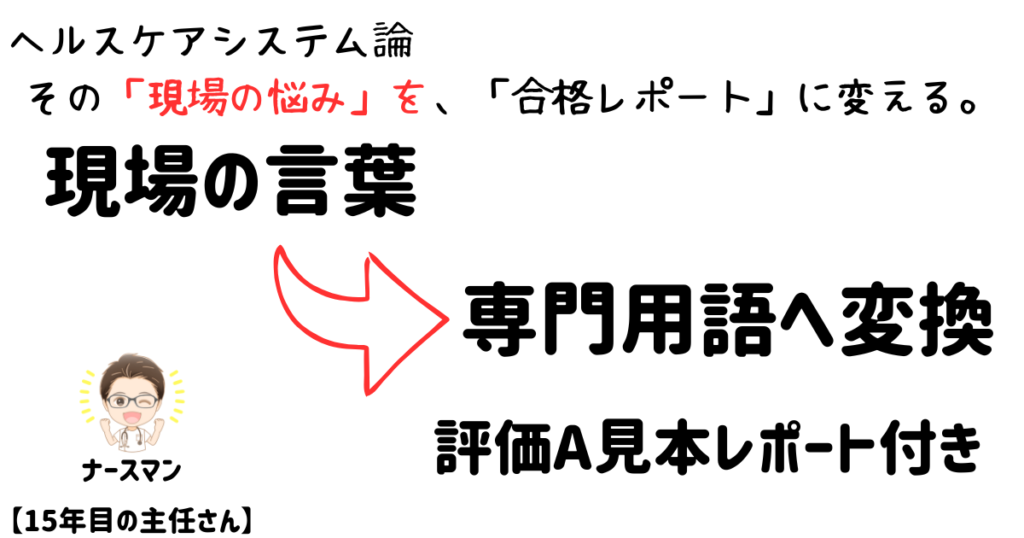
『地域包括ケア』や『2040年問題』…
言葉は知っているけれど、それを自部署の課題とどう結びつければいいか分からず、手が止まっていませんか?
ヘルスケアシステム論Ⅰは、普段の看護業務とは視点が異なるため、受講生が最も「何を書けば正解なの?」と迷う科目です。
現場で起きている「人手不足」や「多忙さ」を、なぜわざわざ難しい言葉に置き換えなければならないのか。
その理由は、看護管理者に求められているのが「現場の視点を、国の政策(システム)の視点に翻訳する能力」だからです。
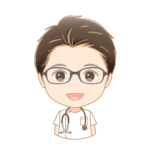
地域特性、政策などに意識向けていく必要があります。
本記事では、評価Aを獲得するための視点の切り替え方と、合格レポートの例文を紹介します。
⇒主任看護師が教える「ファーストレベル全レポート最短攻略マガジン」をチェックする
判定Aを獲るための「魔法のフレーズ」変換例
レポートの評価を劇的に上げるには、キーワードの使い方が重要です。

独居などの高齢者が増えて入院期間が長くなっている
👉魔法のフレーズ
2040年問題を見据えた疾患構造の変化により、地域包括ケアシステムにおける病床機能の最適化が急務となっている
このように、現場の「あるある」をシステム論の言葉へ置き換えるだけで、合格できるレポートのキーワードが生まれます。
評価Aを獲得したレポート見本
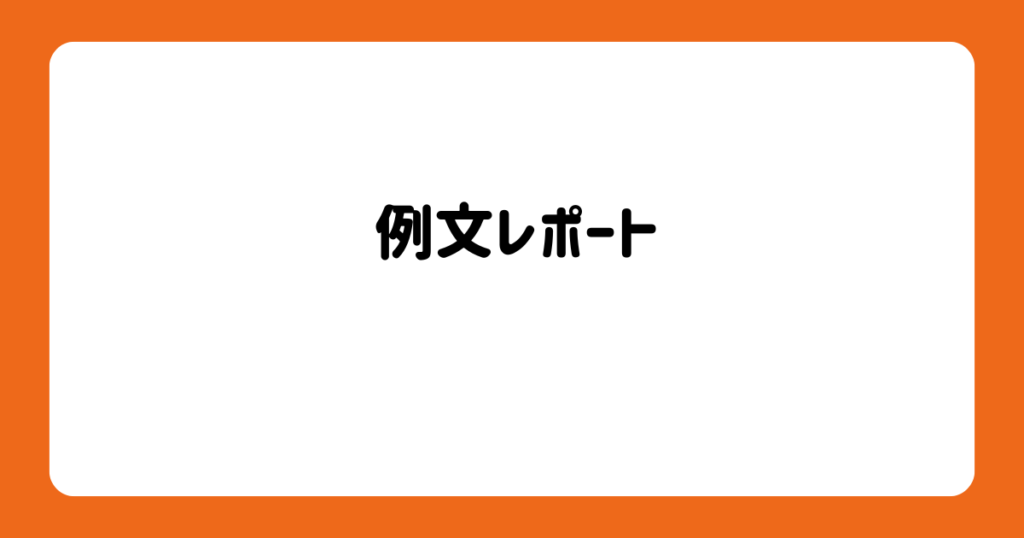
私のnoteでは、実際に評価Aを獲得した「ポリファーマシーと医療経済」をテーマにした、そのまま提出可能なレベルの例文を公開しています。
- 日本の医療システムの『歪み』をどう定義するか?
- 看護管理者がどうシステムに介入すべきか?
これらを論理的に組み立てた見本を収録。
さらに、埋めるだけでレポートが完成する「魔法のフレーズ2パターン」もセットにしています。
私のブログで紹介した構成案を含む、全レポートの攻略法をまとめた『【評価A実績】ファーストレベル全レポート最短攻略マガジン』ですが、今まで多くの方にご活用いただいております
「最短で評価Aを狙いたい」「レポートに追われる日々から解放されたい」という方は、チェックしておくことを強くおすすめします。
まとめ
ヘルスケアシステム論は、自力で考えると時間が溶けていく科目です。
課題が出題されらその日から目処を立てて、安心を手に入れたい
という方のために、最短攻略シートを用意しました。